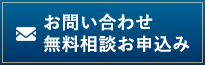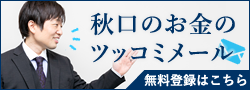事業の倍速コラム。
- 税務メモ 2021/02/15 確定申告 提出期間
- 2021/02/08 青色申告特別控除と申告依頼
- 2021/01/06 固定資産税の減免
- 2020/11/24 税金を払わないとお金が残らない。
- 2020/06/15 住民税
- 2020/05/11 資金繰りの厳しい状況ですが・・・
- 2020/03/02 期限をのばして、得になることなんて何一つない。
- 2020/02/25 すべての個人の税金は、確定申告で決まる。
- 2020/02/10 繰越控除はつかえない。
- 2020/02/03 確定申告に必要な書類とは!
- 2019/12/16 届出書はめんどくさい(特に消費税)
- 2019/11/18 消費税増税後。
- 2019/09/02 消費税増税。
- 2018/12/17 iDeCoとか確定拠出年金とか
- 2018/12/10 税金を減らすと資金繰りが悪化する。
- 2018/11/12 過去の過ち
- 2018/08/20 子や孫への教育資金一括贈与制度
- 2018/06/25 確定申告で確定するもの
- 2018/03/12 納税証明と所得証明
- 2018/03/05 できるだけ負担をかけずに事業を承継したい!
- 2018/02/05 仮想通貨の話題で聞かれる話題。
- 2018/01/29 消費税は払いたくないけれど。
- 2018/01/22 健康保険料(税)と国民年金
- 2017/11/20 お約束の節税対策
- 2017/11/06 年末調整の季節がきやがったぜ!!
- 2017/10/16 なぜ申告をしないといけないのか。
- 2017/04/10 決算終わったら保存しておくもの。
- 2017/03/13 源泉所得税とは?
- 2017/02/26 おっきな封筒(角2)とちっさな封筒(長形3)
- 2017/02/06 正しい手続きと、正しいと思っている手続きで、間違っている事が発覚していないものの違い。
- 2017/01/16 償却資産ってなんやねん!!
- 2016/12/12 ふるさと納税でそんなに肉が食いたいか!?
- 2016/11/14 損失の繰越。
- 2016/11/07 年末調整の季節がやってきやがったぜ!!
- 2016/08/22 届出
- 2016/07/04 予定納税。個人事業の人
- 2016/05/09 将来に対する積立と節税。
- 2016/04/25 相続問題。
- 2015/12/28 住宅取得控除(と還付申告)
- 2015/12/07 会社を設立する価値。
- 2015/07/06 住民税。
- 2015/06/29 二次相続のことを考えていますか?
- 2015/06/22 納期特例。
- 2015/05/18 放ったらかしにしない。
- 2015/03/02 住宅借入金等特別控除。
- 2015/01/26 確定申告の提出期限。
- 2014/12/15 ふるさと納税。
- 2014/11/17 103万円の壁。
- 2014/11/10 年末調整
- 2014/10/27 勘定科目。
- 2014/10/13 初めての給与支払い。
- 2014/09/29 無申告加算税
- 2014/04/27 消費税増税は3%アップではない!?
- 2014/03/17 更生の請求?還付申告?
- 2014/03/03 平成25年度 確定申告の間違いやすい箇所
- 2014/02/17 書類の保存
確定申告 提出期間
2021/02/15青色申告特別控除と申告依頼
2021/02/08固定資産税の減免
2021/01/06| 2020年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
|---|---|
| 50%以上減少 | 全額 |
| 30%以上50%未満 | 2分の1 |
税金を払わないとお金が残らない。
2020/11/24住民税
2020/06/15資金繰りの厳しい状況ですが・・・
2020/05/11期限をのばして、得になることなんて何一つない。
2020/03/02すべての個人の税金は、確定申告で決まる。
2020/02/25繰越控除はつかえない。
2020/02/10確定申告に必要な書類とは!
2020/02/03届出書はめんどくさい(特に消費税)
2019/12/16消費税増税後。
2019/11/18消費税増税。
2019/09/02iDeCoとか確定拠出年金とか
2018/12/17税金を減らすと資金繰りが悪化する。
2018/12/10過去の過ち
2018/11/12子や孫への教育資金一括贈与制度
2018/08/2030歳未満の子供一人につき1500万円までの贈与が非課税になります。
お子様・お孫様に、ご自身がこの世を去った後の教育資金までプレゼントしてあげられて、
相続税対策にもなるという便利な制度です。
あくまで、教育資金ってことですが。
メリット
・贈与税がかからない
・元気なうちに一括贈与
・使途を教育目的に限定して贈与を行うことができる
・暦年贈与との併用が可能
・最後の3年の間に行った場合でも相続財産への持ち戻しがされません。
デメリット
・そもそも贈与は毎年110万円までなら無税
・学費等をその都度子供や孫に贈与するのも無税
・贈与を受け取った人が行う手続きが面倒
・教育資金に該当するか判断が難しい
・子・孫が30歳になった時点で使い切れなかった額に贈与税がかかる
まとめ
確かに受贈者1人につき1,500万円という大きな財産が無税で贈与できるというのは、将来の相続税対策として非常に有効な方法です。
しかし贈与時点では大丈夫だと思っていても、払い戻しはできないので自分たちの老後費用などが想像以上にかかってしまい
贈与のし過ぎを後悔することになる場合もあるかもしれません。
実際は自分の子供にってより、お孫さんに対して利用することが多いですが。
どうせ税金がかかるなら、孫に喜んでもらう為にお金を使うほうが良い。
孫より、そのお子さんの親御さんのほうが喜ぶのでしょうけど。
「都度渡したほうが、そのたびにお孫さんの喜ぶ顔が見れますよ。」
なんて事を言っちゃうと、実行に移せなくなくなる・・・そんな制度というイメージです。
確定申告で確定するもの
2018/06/25納税証明と所得証明
2018/03/12できるだけ負担をかけずに事業を承継したい!
2018/03/05仮想通貨の話題で聞かれる話題。
2018/02/05消費税は払いたくないけれど。
2018/01/29健康保険料(税)と国民年金
2018/01/22お約束の節税対策
2017/11/20年末調整の季節がきやがったぜ!!
2017/11/06なぜ申告をしないといけないのか。
2017/10/16決算終わったら保存しておくもの。
2017/04/10源泉所得税とは?
2017/03/13おっきな封筒(角2)とちっさな封筒(長形3)
2017/02/26正しい手続きと、正しいと思っている手続きで、間違っている事が発覚していないものの違い。
2017/02/06償却資産ってなんやねん!!
2017/01/16ふるさと納税でそんなに肉が食いたいか!?
2016/12/12損失の繰越。
2016/11/14年末調整の季節がやってきやがったぜ!!
2016/11/07届出
2016/08/22予定納税。個人事業の人
2016/07/04将来に対する積立と節税。
2016/05/09相続問題。
2016/04/25住宅取得控除(と還付申告)
2015/12/28会社を設立する価値。
2015/12/07住民税。
2015/07/06二次相続のことを考えていますか?
2015/06/29納期特例。
2015/06/22放ったらかしにしない。
2015/05/18住宅借入金等特別控除。
2015/03/02確定申告の提出期限。
2015/01/26ふるさと納税。
2014/12/15103万円の壁。
2014/11/17年末調整
2014/11/10勘定科目。
2014/10/27初めての給与支払い。
2014/10/13無申告加算税
2014/09/29消費税増税は3%アップではない!?
2014/04/27更生の請求?還付申告?
2014/03/17平成25年度 確定申告の間違いやすい箇所
2014/03/03書類の保存
2014/02/17- 2021/06
- 2021/05
- 2021/03
- 2021/02
- 2021/01
- 2020/12
- 2020/11
- 2020/10
- 2020/09
- 2020/08
- 2020/07
- 2020/06
- 2020/05
- 2020/04
- 2020/03
- 2020/02
- 2020/01
- 2019/12
- 2019/11
- 2019/10
- 2019/09
- 2019/08
- 2019/07
- 2019/06
- 2019/05
- 2019/04
- 2019/03
- 2019/02
- 2019/01
- 2018/12
- 2018/11
- 2018/10
- 2018/09
- 2018/08
- 2018/07
- 2018/06
- 2018/05
- 2018/04
- 2018/03
- 2018/02
- 2018/01
- 2017/12
- 2017/11
- 2017/10
- 2017/09
- 2017/08
- 2017/07
- 2017/06
- 2017/05
- 2017/04
- 2017/03
- 2017/02
- 2017/01
- 2016/12
- 2016/11
- 2016/10
- 2016/09
- 2016/08
- 2016/07
- 2016/06
- 2016/05
- 2016/04
- 2016/03
- 2016/02
- 2016/01
- 2015/12
- 2015/11
- 2015/10
- 2015/09
- 2015/08
- 2015/07
- 2015/06
- 2015/05
- 2015/04
- 2015/03
- 2015/02
- 2015/01
- 2014/12
- 2014/11
- 2014/10
- 2014/09
- 2014/08
- 2014/07
- 2014/06
- 2014/05
- 2014/04
- 2014/03
- 2014/02
- 2014/01
- 2013/11
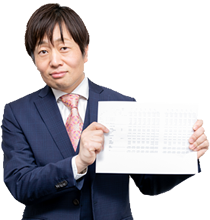
まずはお茶でも飲みに来ませんか?
そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。
税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。
ご希望の方には、秋口特製の『未来こうなるシート』を後日お送りします。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階 事務所概要はこちら